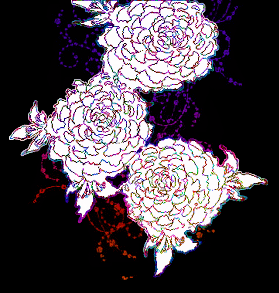
まるで情緒のない直接的なセックスは、私たちによくお似合いだと思う。つかの間の激しさに身を任せたあとは、なんとなく元気になって、すっきりする。だから、体の中に煩わしいものがあるときほど会いたくなるのだ。 着痩せして見えるけれど実は筋肉質な背中に、赤い爪痕が残っている。だけどそのことにまったく触れてこないのが、彼らしいと思う。この男と寝ているときだけは何も考えなくていいし気を使わなくていい。きっとこの男には他人に気を使わせない才能があるのだろう。普段からそういった節はあるものの、セックスに関しては抜群にその才能を発揮してくれている。ありがたいとさえ思う。 「腹減ったな、コンビニ行くか」 情緒のない科白をきっかけに、太刀川はベッドから立ち上がった。シャワーも浴びずに、床に落としていたTシャツをかぶる。 「ついでにDVDでも借りるか。ヒマだし」 「いいけど」 汗ばんだ体にまとわりつくシーツが、ここから起き上がる気力を奪う。それに眠い。そう思いぐずぐずしていれば、「行かねえの?」と大して急かすつもりもなさそうな声が飛んでくる。 「私、シャワー浴びたい」 「ふーん?じゃあ俺一人で行くか」 「ビール飲みたいかも」 「ついでに買ってきてやるよ」 私のワガママを気に留める様子もなく、太刀川は財布と携帯だけをポケットに押し込んであっさりと出て行った。鉄製の重いドアが、音を立てて閉まる。たった7畳しかないワンルームマンションは、彼にとっては唯一の住居だけれど、私たち2人が揃うとどこよりも落ち着けるラブホテルと同意だ。でも純粋な愛情はここには無い。 付けっぱなしだったエアコンを切って、のろのろとベッドから出た。テーブルの上のペットボトルはキャップがゆるんでいる。きっと中のコーラは気が抜けているだろう。体の中を燃やし尽くすようなセックスの後の甘ったるいコーラは、あまりにもこの部屋にお似合いで笑えてしまう。 シャワーを浴びて硬いタオルで体を包んだ格好のまま、適当にテレビを点けた。まだ日が沈みきらない日曜日のこの時間は、集中できる番組なんて1つも流れていない。DVDを借りてくると言った太刀川は、何を選んでくるだろう。ハリウッドの派手なアクションものか、それとも昔の連続ドラマか。私は別に、彼が何を選んでこようと、どうでもいい。彼の趣味が何であろうと、それが私と真逆なものであろうと、気にならない。私は彼のことは好きじゃない。だから、帰ってくるであろう彼の手にビールの入った袋さえあれば、それでいいのだ。 ―俺は別に何も聞かないからな。 初めてこの部屋に足を踏み入れたとき、太刀川は缶ビールを煽りながらそう言った。くっきりと浮き出た喉仏が、やけに性的だと思った。今思えば、あれは彼にとって最大限の誠意だったのだろう。いざお互いが触れ合ってしまう前に、認識を揃えておこうとしたのだと思う。 「俺はお前をただの都合のいい女ってことにするけど、それでいいんだよな?」 渇いた眼差しがまっすぐ私を捉えた。彼のそんな表情を、私はあのとき初めて見た。この男は、私を求めていない。私にはまるで興味がない。でも、そんな男でないと、きっとだめだった。 「私も、太刀川には何も求めないから」 「・・・何も?」 「・・・・・・何も、は、嘘」 ただめちゃくちゃに抱いてほしい。セックスという至上の方法で、私を女扱いしてほしい。彼は、私がそう言葉にしなくても、そうしてくれた。自分を愛していない男と寝ることはとても気が楽だった。自分が愛している男と寝るより、ずっと。 太刀川が借りてきたDVDは、予想に反して、昨年流行った恋愛映画だった。この映画では脇役だった女優がこれをきっかけに大ヒットして、今クールのドラマの主役を務めている。 「俺、この子結構好きなんだよな」 なるほど、恋愛映画なんて興味がなさそうなのにこれを選んだ理由が分かった。私は与えられた缶ビールを少しずつ飲みながら、ぼんやりと画面を眺めていた。私はこの作品を、昨年きちんと映画館で観た。隣にいたのは、好きな人だった。女の子と映画を見るなんて久しぶりだ、と少し笑いながら付き合ってくれた。その人は、私のことなんてちっとも好きじゃなかった。それがわかってしまったから、私はあの日の夜、太刀川の部屋を訪ねたのだ。 「・・・この映画、ちっとも面白くない」 「ん?何だよ、お前、恋愛系嫌いなんだっけ」 嫌いじゃない。でも、見たくない。胸の中で掻きむしりたいような焦燥感が暴れまわる。あの人と一緒に見つめたスクリーンを、今こうして太刀川と並んで見ているなんて。ろくでもないことをしていると思う。 「・・・太刀川、消して」 私の言葉に、太刀川は黙ってテレビを消した。そして些か乱暴に、私を床に押し倒した。ビールのにおいのする唇同士を重ね合わせる数秒間で、また体の中が濡れ始めるのが分かる。こうして何も考えずに、愛情の欠片もないセックスをすることだけが、崩れ落ちそうな心を守る唯一の方法。それを与えてくれるこの男だけが―。 ずり上がったTシャツをじれったそうに脱がされて、脇のあたりに彼の顔が埋まる。愛する男になら触れられたくないそこに、熱い舌が這う。研ぎ澄まされた性感が少しずつ思考にノイズをかける。 「・・・俺、お前とやってる時が一番いいわ」 木の葉のように体をひっくり返されて、耳元でそう囁かれる。ぞくりと首筋が粟立つと、それを無遠慮に舐め取られ、私の喉から声にならない声が漏れ出る。 「他の男の代わりに抱いてやってるんだって思うと、何でもしてやろうって気になる」 強く目を瞑れば、彼の言う『他の男』の横顔が、簡単に浮かび上がった。繊細そうな眼差しに青い光を灯して、いつも、ずっとずっと遠くを見ている人。私にも、他の誰にも等しく優しくて、そしてその分だけ、残酷に私を傷つける。やわらかな声で名前を呼ばれる度に、どうかこの人に女として愛されたいと、そう思い続けてきた。 毛の長いカーペットに爪を立てたらその手ごと絡め取られて、後ろから抱きすくめられながら、ただ律動を受け入れる。あ、あ、とせり上がる声が部屋の中に響く。ふと目線を向けると、さっきまで映画が流れていたテレビの黒い画面に、今の私たちの影が映っていた。どこまでも浅ましくて愚かしい、最低な女がそこにいた。 「・・・なあ、あいつのどこがいいんだよ?」 「いや・・・、そんなの、」 「ほら、言ってみろよ、あいつにしてほしいこと」 俺が全部代わりにしてやるよ。 まるで麻薬だ。脳髄から痺れそうな、甘い誘惑。気の抜けたコーラよりずっと甘ったるくて、ずっと舌の上にこびりつきそうな。一度知ってしまったら、また何度も何度も求めてしまう。だから決して、口に出してはいけない。 A Scapegoat Rock'n'roll |
