昨晩ずっと降り続いた雪のせいで、今朝の瀞霊廷は一面銀世界になっている。 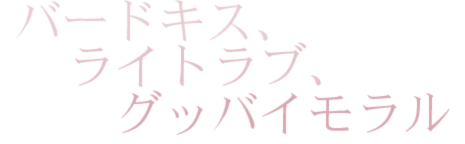 はらはらと雪が舞い落ちる中、寒い寒いと無邪気に声を上げながら雪かきに勤しんでいるのは、五番隊に属するだった。隊長である平子は隊舎の窓越しにその姿を見つけると、ふと足を止めた。石油ストーブの焚かれたこの部屋も、窓際までやって来れば外の冷えきった空気が伝わってくる。時折自分の呼気で白く曇る窓硝子に指を這わせ、平子は外の様子をじっと窺った。 雪かきをしているのは、半年前に異動してきたと、五番隊の十席に身を置いている若い男性隊員だった。真面目な隊員の多い五番隊の中で、この男も例に漏れず真面目で申し分ないのだが、平子は最近、ほんの少し、彼に対して妙なものを感じてしまう。それは例えば濁った水底に沈む汚泥のような、普段は目に触れないけれど確実にそこにあるというような、そんなものによく似ていた。 そのとき、窓硝子の向こうにいるが、ふっと平子の方に気がついた。それまで楽しげに笑っていた表情が一瞬で冷静なものになる。それに気付いた男性隊員も、の視線を追うようにして平子の方を振り返った。2人と視線が合ってしまった平子は、仕方なくカラカラと音を立てて窓を開ける。1つ息を吐くとそれはすぐに白い靄になった。 「寒い中ご苦労さん」 平子が緩慢な口調で言うと、十席の男は「おはようございます!」と威勢よく声を上げて腰を折った。その腰の角度に五番隊の気風が滲み出ている気がして、平子は思わず苦笑を噛み殺すも、隣に突っ立っていると目が合うと、その苦笑は噛み殺されずに漏れ出した。自分の隣で上司が深々と腰を折っているというのに、はその対象に対して頭を下げぬどころか、へらりと緩い微笑みを向けているのだ。不躾としかいえないその態度も、なぜかこの雪の中ではやけに清廉として見えた。 「そない畏まらんでもええて。…まァ、もう1人はずっと顔上げとったけどな」 顔を上げた十席の隊員は、慌てたようにを見た。しかしは悪びれる素振りもなく、積雪の中へとショベルの先を埋める。ざくり、と手応えのありそうな音がした。 「平子隊長も一緒に雪かきされませんか?楽しいですよ」 「なっ、何言い出すんださん!」 男が慌てて怒鳴ったが、は雪かきの手を止めぬまま、顔を上げようともしない。おそらく男は本気で焦っているのだろうが、それは本当にその男だけのことで、も、そしてもちろん平子も、何らこの状況に違和感を覚えていない。もしもここでが神妙に「すみません」なんて言おうものなら、その方が二人にとっては慌てるべきことだ。 「申し訳ありません、平子隊長」 雪かきをやめないに代わって、男が頭を下げた。その様に、平子はほんの少しの不満を感じながらも、片手をひらひらと振って「ええねん」と短く言ってやる。するとおずおずと顔を上げた男の後ろで、がひっそりと顔を上げ、そして男に気付かれぬように笑ってみせた。悪戯っぽく目尻をきゅっと下げたその笑顔に、平子は笑い返してやるわけにもいかず、黙って窓を閉めてしまった。 その態度を平子の不機嫌と見なした男は、窓の向こうに消えてしまった平子の影を目で追いながら、弱々しく溜息をついた。ちらりと横を見れば、機嫌を損ねた張本人である部下が、相変わらず楽しそうに雪かきに勤しんでいる。 「……さん、…君の教育係である僕の面子ってものも少しは考えてくれないかな」 まるで諦めたようなその口調がおかしくて、は雪の地面を見ながらふふっと小さく笑った。 『共犯者』という言葉が一番しっくりくる。五番隊の隊風には馴染まぬあの奔放な女のことを考えるとき、平子はその不安定な秘密性に、つい眉間に力を込めてしまう。他人の貞操観念や倫理観なんてものにとやかく言及するつもりは無いが、どうしても、あの女の横顔を見ていると、何か1つ言ってやりたくなってしまうのだ。と自分が寝たのはたった2度のこと。しかしその2度というのが厄介で、どうして1度で済まなかったのだろうと思う。 窓から離れてしまうと、もう外の気配は感じ取れない。2人はまだそこにいるだろうか、それとももう寒さに参って隊舎の中に戻ってしまったか。また外を覗けば簡単に分かることなのだが、もしまだ2人がそこにいたら、と思うとそうは出来なかった。再び顔を合わすことの気まずさなんてものはどうでもいいのだが、その2人が雪の中にいる、そのことが、平子にとっては気に入らなかった。 「平子隊長?」 そのとき、部屋の扉の外で声がした。石油ストーブの前に座り込んでいた平子は扉の方に目を向ける。こんな朝から隊首室を訪ねてくる人物など、思い当たるのは副隊長である藍染くらいしかいない。しかしその声は藍染のものではなかった。 平子はすっと立ち上がると、返事をするより先に扉に手を伸ばした。立付けのいい扉が音を立てずに開かれる。同時に冷たい空気が吹き込んできたが、それ以上に平子の表情を険しくさせたのは、そこに立っていた人物そのものだった。 「…平隊員が簡単に来てもええ部屋とちゃうねんで」 わざとつっけんどんに言った平子に対し、目の前の女は歯を見せて笑った。その瞬間、ほろりと何かが輝いたような気がしたが、それが何であるかはわからなかった。そして平子はその正体を突き止めることをせず、女の手首を乱暴に引っ張って部屋の中へと招き入れた。外に誰の気配も無いことを、きちんと確認した上で。 「…簡単に連れ込んでいい場所でも、ないと思いますけど」 平子が扉を閉めると同時にはそう言った。いつもの、他人を試すような、生意気そうな瞳のまま。平子は忌々しげにその顔を見下ろすと、わざとらしく大きな溜息をついた。自分の肩口にあるの小さな頭が、くたりと傾げられる。 石油ストーブのにおいに混じって、すぐ傍にいる女から、外の冷たいにおいがする。きっとその白い肌は見た目よりずっと凍えてしまっているのだろうと、うっかり頬に手を伸ばしそうになったが、平子はそれを気付かれぬように堪えた。ここでそうやって触れてしまったら、後のことは、否が応でも想像できてしまう。 「…で、何の用やねん」 平子はどすんと音を立てて、応接用の革張りの椅子に腰掛けた。は扉の前に立ったまま動こうとしないが、その目線だけはしっかりと平子を追っている。 この、意味ありげな目に見つめられると、平子は居心地が悪くなってしまう。しかしその居心地の悪さはなぜか癖になってしまうもので、一旦目線を外しても、再び見つめ返してしまうのだ。の華奢な体の線が、とても寒そうに見える。 「面子を繕いにきたんです」 は真面目な表情のまま言った。今度は平子が首を傾げる。 「…面子?」 「ええ。すごく不安がっていらっしゃったので」 「…何の話や」 「私が十席の先輩の面子を潰してしまったのなら、私が繕いに来なければならないと思って」 どういう感情の下でそう言っているのか、の凛とした表情からでは分からない。しかし台詞の中に登場したある単語のせいで、平子の機嫌はすこぶる悪くなった。その機嫌の変化はまるで折れ線グラフを描くように、はっきりと自覚できる程のもの。 平子の苛立ちに気付いたのか、は不思議そうに目を丸くした。しかしそのことにびくびくしたり、上司の機嫌を取ろうとしたりするような隊員ではない。そうしてだんまりを決め込むのなら自分の言い分だけでも言ってしまおうと、焦ることなくゆったりと平子の前まで足を進めた。一歩ずつ近付いて来る、さらさらという衣擦れの音を、平子は黙って聞いていた。 「私の態度の悪さは、十席の先輩の教育のせいでは決してございませんので」 「………それを『言いに行け』て、あいつに言われたんか?」 「いいえ、私の意思で申し上げに参っただけです」 がこれほど改まった言葉遣いを用いるのは、入隊直後に顔を合わせた時以来のことだった。本来なら気にも留めない、至って普通の言葉遣いなのだが、目の前にいるのがだということが、平子にとっては気に入らない。 その不機嫌さを隠そうとせず大仰な溜息を吐き出してみれば、はにこりと微笑んで頭を下げた。もう少し申し訳なさそうな顔をしてみればいいのに、と平子は思う。そうすれば少しは、自分のペースを取り戻せるのに、と。 「では、私はこれから十席の元で剣道の稽古がありますので、失礼致します」 は表情1つ変えずにそう告げると、足早に出口の方へ向かい、すっと扉に手を伸ばした。その白い腕は立付けのいい扉を容易く開けて、間もなく冷たい空気を部屋に吹き込ませる、筈だった。しかしその扉は開かなかった。いつの間にかの真後ろに立っていた平子が腕を伸ばし、が扉を開けようと力を込めた方向とは反対の向きに、扉を押さえつけていたからだ。 扉を開けようとすると、そうさせまいとする平子の、無言の攻防は暫く続いたが、そのうちふっとが手から力を抜いた。そして観念したようにゆるゆると振り返る。そうすれば思ったより近いところに、平子の薄い胸があった。視線を上げた先にある端整な顔には、不機嫌そうな表情が貼り付けられたまま。 「…どうして怒ってるんですか?」 そう言ったは、にやりと意味ありげに笑っていた。もう少し不思議そうな顔をするかと思っていた平子は、不覚にも面食らってしまう。しかしそれでこそという女だという気もする。でなければこうして、自分の部屋に引き入れるようなことはなかっただろう。 「怒ってへんわ」 「怒ってるじゃないですか」 「俺はもともとこんな感じや」 平子は平静を装って言ったのだが、水晶玉のようなの瞳を見ていると、何もかも見透かされているような気がしてしまう。しかしその瞳には、相手のことを見透かす以外の何か不思議な力があるように思えて、やはり視線を外せない。きっとこれがの持つ底なしの魅力なのだと平子は思う。 はそれまで肩越しに平子の方を見上げていたのだが、ゆっくりと体ごと正面を向くと、にこりとその口角を吊り上げた。桜色に塗られた唇が、光の加減で絶妙に艶かしく光って見える。 「怒ってないなら稽古に行かせてくださいよ」 「…何やねん、問題児のくせに、そない稽古したいんかいな」 「ええ、十席の先輩がせっかくお手合わせして下さるとのことで、お待ちですから」 そこまで言われて、平子はようやく自分が試されているのだと認めざるを得なくなった。目の前にいる不真面目な部下は、隊長である自分のことを、からかい半分で試している。どう言えば心を乱すか、どういう表情をすれば本音を引き出せるか、それはまるでゲームのように。平子は頭を抱えたくなった。 普段の平子はこんなとき、大人しく試されて甘んじるような性質(たち)ではない。しかしどうしてか、この女を前にすると、その甘ったるさに身を投じてもいいかと思ってしまうのだ。誘うとか迫るとか、そんな安っぽい言葉ではについては語れない。魔性の女というありふれた言葉も、できるなら用いたくない。ただ言えるのは、何にも例えられないこの女を他の男に渡したくは無いという、至極単純な、しかし道理の立たない、独占欲の存在だけだ。 「…手合わせやったら俺相手の方が勉強になるやろ」 「…そんなこと、私の口からは十席に伝えられませんよ」 特に困った風でもなくは言ってのける。その小生意気な口元を平子は見つめた。そうすると否が応でも思い出されるのは、抱き合った二度の夜のこと。ぞくりと今にも背中が粟立ちそうになる。 「…あんな男の稽古なんざ、無断欠席上等や」 声音を低くして耳元で囁いてやれば、先程まで気丈だったが、ひくりと肩口を震わせた。そのまま大人しくなるかと思えば、の細い指先は、躊躇うことなく平子の死覇装の襟元を探る。軽く乱された襟から冷たい指先が入り込んで、平子はそれにより上昇する自分の熱情を気取られぬように、少々乱暴に、の体を扉に押し付けた。 は熱っぽい息を一瞬漏らし、その冷たい手で無遠慮に平子の首筋を撫ぜる。そしてそのまま、自身の頬を平子の首筋に摺り寄せて、ぼそりと囁いた。 「…十席の稽古をさぼったら、」 「…あ?」 「また面子を繕いに来なきゃいけなくなるじゃないですか」 今度こそは、惜しげもなく艶かしい笑みを浮かべた。至近距離で目にするその表情に、平子は堪えきれぬというように、噛み付くようなキスをする。 (― これで三度目や) 今自分の腕の中にいる女は、自隊の不真面目な部下である。それでもこうして触れるための理屈が、触れたいと思う回数の分だけ存在すればいいのに。そんなことを願っていたのは、きっと平子だけではない。 e n d |